「サクランボ食べたいーっ!」と駄々こねて山形へ。 6月も後半では、もう終わっちゃったかなー・・・ とドキドキしながら、今年は天童へ行ってみました。 無い・・・道端の直売所も軒並み閉まってる(汗) 「道の駅まで戻ってみる?」と新月サン。 とか言ってたら、一軒開いてるお店がありました。 「こっちが3Lで、こっちが2Lね。 一個だけLあるけど。」とお店のおっちゃん。 5パックあった3Lを買い占めて帰りました。 来年はもうちょっと早く来なきゃだわ。
 筆者がずるして楽をしていると言われそうですが、7月のスーパースージーにはマミポコさんの「お嬢01Wレストア計画」を掲載する予定で、昨日取材させていただいた「ワンオーナーで30年」は、11月まで温存のつもりでしたが、後述の展開で9月に前倒しとなります。11月の号には本来9月の予定で「Cyber‐Kさんによる林道インプレッション」を書いていただきました。なんかもうややこしいんですが、入稿の入れ替えです。
筆者がずるして楽をしていると言われそうですが、7月のスーパースージーにはマミポコさんの「お嬢01Wレストア計画」を掲載する予定で、昨日取材させていただいた「ワンオーナーで30年」は、11月まで温存のつもりでしたが、後述の展開で9月に前倒しとなります。11月の号には本来9月の予定で「Cyber‐Kさんによる林道インプレッション」を書いていただきました。なんかもうややこしいんですが、入稿の入れ替えです。
Kさん、原稿には書いていませんが、林道の走り方やリスク回避に基づいた運転者が、最新のSUVになるほどできていないと話していました。最新でなくとも慣れによる煩雑な運転は傍から見ていてはらはらすると。
そういうところも辛口に出してもらったら良かったのですが、残念ながら文字数の関係もあり書き足してと注文できません。ESPに始まる電子制御デバイスが、林道走行程度のステージだと危険回避意識のハードルを下げてしまうのかもしれません。
逆の視点で見ると、Kさん曰く「AllGRIPはモードセレクトで荒れた道も安定して走れる」という部分から、四代目がオンロード寄りになったとだけ評価するのはどうなんだ?とアピールしたいそうです。
 それでもエスクードの系譜はラフロードを逞しく走ることではないのかと、Kさんは自車のラフロード仕様化を行い、あらかじめ組んでいたサスペンションをはじめタイヤやバンパーガード、ルーフラックを組んだわけですが、その様子を動画にしております。さあ、中身は羊のままか。羊の皮を被ったのか。この話が舞い込んできたので、林道編からラフロード化編へと年越し前後編の流れを作ります。ことし30年のエスクードは、ことしのうちに掲載しなくてはならないからです。
それでもエスクードの系譜はラフロードを逞しく走ることではないのかと、Kさんは自車のラフロード仕様化を行い、あらかじめ組んでいたサスペンションをはじめタイヤやバンパーガード、ルーフラックを組んだわけですが、その様子を動画にしております。さあ、中身は羊のままか。羊の皮を被ったのか。この話が舞い込んできたので、林道編からラフロード化編へと年越し前後編の流れを作ります。ことし30年のエスクードは、ことしのうちに掲載しなくてはならないからです。
 本日、スーパースージー掲載用の取材を行うのですが、コロナ禍対策で一グループ五人までしか入店できないことから、取材対象の人以外にお知らせをしておりません。でもたぶん、「つくばーど®in〇〇」とか言ってリポートは書いてしまうので、先にお詫びしておきます。「別のグループですっ」と言い張って開店と同時に席をとるという手もありますが、人気店なので早く行かないと満席になること必至です。そこまでしてでも冷やかすぞの人は、抑止できませんと逃げておきます。
本日、スーパースージー掲載用の取材を行うのですが、コロナ禍対策で一グループ五人までしか入店できないことから、取材対象の人以外にお知らせをしておりません。でもたぶん、「つくばーど®in〇〇」とか言ってリポートは書いてしまうので、先にお詫びしておきます。「別のグループですっ」と言い張って開店と同時に席をとるという手もありますが、人気店なので早く行かないと満席になること必至です。そこまでしてでも冷やかすぞの人は、抑止できませんと逃げておきます。
 閑話休題というか、インターミッション。ということで、お詫びの通り「つくばーど®inらいとにんぐ笠間」を掲載しました。
閑話休題というか、インターミッション。ということで、お詫びの通り「つくばーど®inらいとにんぐ笠間」を掲載しました。
それはいいけど(いいのか?)、3台のエスクードと共にフィガロで臨んでいる構図はいろいろ無謀です。
 我が家で所有していたGリミテッドノマドは、維持し続けていたら今年が30年目でした。これ1台で充分だったのですが、当時は89年式のヘリーハンセンリミテッドと2台体制で家族全員の旅行に出かけていました。ヘリーハンセンは95年にカタログモデルのV6ショートに切り替わりましたが、ノマドは現役続行としたものの、親父が裏切りJB23なんか買ってしまったので、乗り手がいなくなり退役しております。
我が家で所有していたGリミテッドノマドは、維持し続けていたら今年が30年目でした。これ1台で充分だったのですが、当時は89年式のヘリーハンセンリミテッドと2台体制で家族全員の旅行に出かけていました。ヘリーハンセンは95年にカタログモデルのV6ショートに切り替わりましたが、ノマドは現役続行としたものの、親父が裏切りJB23なんか買ってしまったので、乗り手がいなくなり退役しております。
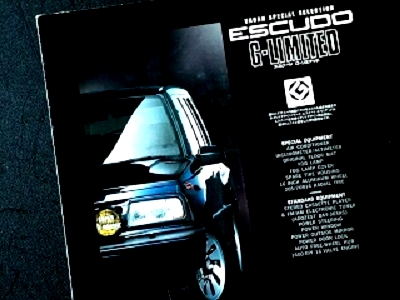 今さら無いものを相手に「たら、れば」な話をしても仕方がないのだけれど、30年を維持したクルマは、我が家にはありません。ぷらすBLUEが32年目というのは年式ベースのことで、僕が購入してからはまだ20年も経っていませんから。それを考えると、クロさんやぴるりさんがワンオーナーで30年目って、ものすごいことだと。これを取材しないでなんの「エスクード誕生35周年」かと、勝手に決めつけ明日敢行です。
今さら無いものを相手に「たら、れば」な話をしても仕方がないのだけれど、30年を維持したクルマは、我が家にはありません。ぷらすBLUEが32年目というのは年式ベースのことで、僕が購入してからはまだ20年も経っていませんから。それを考えると、クロさんやぴるりさんがワンオーナーで30年目って、ものすごいことだと。これを取材しないでなんの「エスクード誕生35周年」かと、勝手に決めつけ明日敢行です。
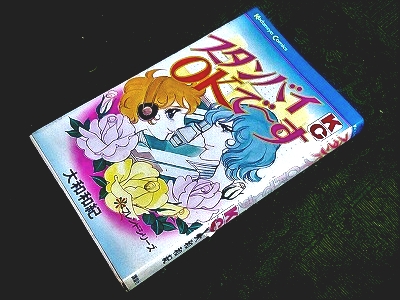 知らずに過ごしていて驚きましたが、ラジオDJを題材とした漫画って、引用させてもらうサイトによれば27作品もある。最近手を染めた「波よ聞いてくれ」以外、まったく読んだことがありません。
知らずに過ごしていて驚きましたが、ラジオDJを題材とした漫画って、引用させてもらうサイトによれば27作品もある。最近手を染めた「波よ聞いてくれ」以外、まったく読んだことがありません。
で、このリストにすら無い、無いのも無理はなくドラマ自体が「放送局」でテレビもラジオもひっくるめられているからの「スタンバイOKで~す」を屋根裏から持ってきました。
「はいからさんが通る」の大和和紀さんが、それよりも前に描いた短期連載物で、単行本が出てからはや半世紀です。3人の女子大生がそろって放送局に就職し、1人は庶務、1人はテレビニュース、もう1人がラジオパーソナリティーになっていくラブコメで、僕が読んだ最初の少女漫画でした。70年代前半は、FM放送よりもAМ局の深夜放送に傾倒した頃で、地元茨城のIBSなどはローカル局でありながら人気DJを多数輩出する、聴いていないと翌日の話題についていけない(小学生がだよ)ひとつの文化でした。
 そんな時代に同級生から貸してもらった少女フレンドに載っていたこの漫画が、当時妙に琴線に触れましたが、今になって強引に「波よ聞いてくれ」に結びつけようとすると、大和さんが札幌の出身だということ。「波よ~」の作者である沙村広明さんは千葉県出身で70年の生まれだから、この漫画をご存じかどうか不明ですが、札幌舞台のラジオ局というキーワードが、細い線で「スタンバイ~」と触れているような気がします。
そんな時代に同級生から貸してもらった少女フレンドに載っていたこの漫画が、当時妙に琴線に触れましたが、今になって強引に「波よ聞いてくれ」に結びつけようとすると、大和さんが札幌の出身だということ。「波よ~」の作者である沙村広明さんは千葉県出身で70年の生まれだから、この漫画をご存じかどうか不明ですが、札幌舞台のラジオ局というキーワードが、細い線で「スタンバイ~」と触れているような気がします。