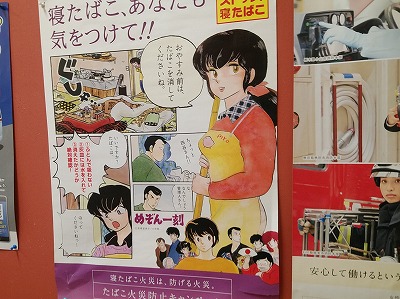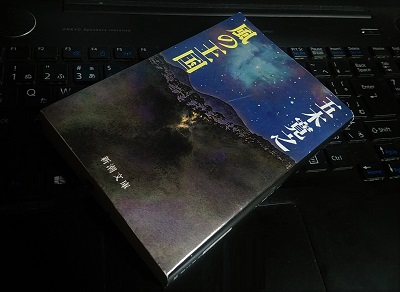昔、「グレートマジンガー」で暗黒大将軍が戦死した折、敵味方ともに彼の弔いをやったような演出があって、それほどに勇猛な幹部であり宿敵だったということなのですが、その喪が明ける(らしい)とき、ミケーネの闇の帝王は「四十九日が過ぎた」などとぬかして、次の回で地獄大元帥の登場となっていくのでした。
昔、「グレートマジンガー」で暗黒大将軍が戦死した折、敵味方ともに彼の弔いをやったような演出があって、それほどに勇猛な幹部であり宿敵だったということなのですが、その喪が明ける(らしい)とき、ミケーネの闇の帝王は「四十九日が過ぎた」などとぬかして、次の回で地獄大元帥の登場となっていくのでした。
古代ギリシアの宗教観なのかそれはっ
いかにも昭和の東映動画な、シリアスさを追求するあまりの落とし穴だったと思います。いや、ひょっとすると古代ギリシアの神話の中にはそのような弔いの仕方があったのかもしれませんが、さすがに四十九日という言葉は聞いたことないです。
それにしても、人が没して七日ごとに審判を受けるというというのは、亡くなった当人も大変だろうなあと感じます。その審判によって来世のありようが決まり、来世に往くまでのどれだけの間、極楽か地獄かにとどまらねばならない。このあたりは死者の国だったりタルタロスだったりエリシオンに落ちていった古代ギリシアの人々の宗教と共通する部分もあるので、ミケーネの闇の帝王が大乗仏教っぽいことを口走っても良いのかも(でも、当時は「変なの」と思ったよ)
 そんなことを思い出して、本日親父の四十九日に臨む僕はスクランブルダッシュな不謹慎野郎です。ことのついでにグレートブースターばりの間抜けな我が家の話を暴露すると、
そんなことを思い出して、本日親父の四十九日に臨む僕はスクランブルダッシュな不謹慎野郎です。ことのついでにグレートブースターばりの間抜けな我が家の話を暴露すると、
「墓参用に千円分の花を四束買ってきて」
と娘らに指示を出した妻でしたが
「一応それで四束買ってきましたよ」
といういわゆる「使えない買い物」に怒り出す始末。冷静に考えなさいよ娘らよ、花屋が千円分なんて「売れ筋にもならない」束を作り置きしているわけないじゃん。
 しかしこちらも冷静に考えると、こいつら肉屋に行って「豚こま200グラムとひき肉300グラム」なんて買い物したことない世代だわ。そもそも町の肉屋が絶滅しているし。
しかしこちらも冷静に考えると、こいつら肉屋に行って「豚こま200グラムとひき肉300グラム」なんて買い物したことない世代だわ。そもそも町の肉屋が絶滅しているし。
という顛末で、なぜか僕が追加で「千円分を二束作って」と買いに駆り出されたので、花屋で演出用の写真を撮らせてもらいました。