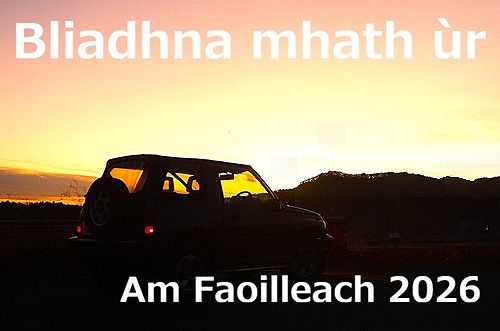東京に勤め出したころは、それこそ葛飾ハープ橋すらなかったものの、もう少しあちこちから富士遠望ができていたと思うんですよ。でもいくつかの「富士見」の地名から富士山が見えなくなったように、中央環状線からも眺めの利く場所が少なくなりました。良いも悪いもリモコン次第なら、僕は鉄人28号で高層建築をぶち壊しに行くんだろうな。
ふと気がつけば、BLUEらすかることТD61Wは「30年前のクルマ」になってしまいました。BLUEらすかるΩことТD61Wも、いくらか新しいけれど「29年前のクルマ」です。この2台の交替が、ついにこの冬に待ち受けています。春風高校光画部の天野小夜子部長はドラマCDにおいて「老いては名馬も駄馬にも劣る」などと言ってますが、年経た馬は路を忘れず、経験を積んだ者は判断を誤らない、との例えもあります。らすかるのあとを継ぐΩは、きっと老馬の智をも受け継いでいくものと信じております。
ただ、この故事の由来である春秋時代の斉の第16代君主・桓公(かんこう)は、散々苦労して偉くなったものの、その後は傍若無人も相まってろくな最期を迎えてもいないという、そっちは見習わんほうがいいなあと思わされる人物。もっとも、道に迷った彼に馬を放ち帰路を導かせたのは宰相の管仲の方ですから、老いたる馬ならぬ老いてきた自分の経験値は、少しくらいはあてにしてもいいだろうと日和るのであります。
12年前の午年の正月、「塞翁が馬」について書いています。その頃、BLUEらすかるはまだ50万キロで月から地球への帰還途上でした。いろいろ皮算用をして2025年末に100万キロをもって退役というシナリオをその後描くわけですが、そうは問屋が卸さなかった昨年のラストステイン。100万キロまでまだ約4000キロを残しています。まさしく塞翁が馬なお話ですが、これほど付き合えたエスクードですから、少しでも長く路を示してくれたらありがたいことです。
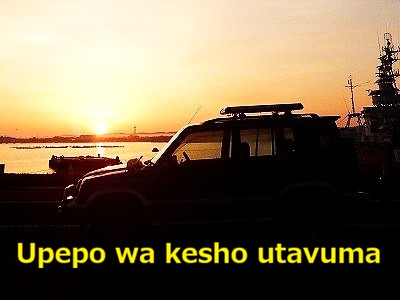 緊急入院の末病室で始まった2025年もどうにかこうにか大晦日まで這い蹲ってこられました。この1年で体重が30キロ削れました。例年並みのペースで5万キロ弱、BLUEらすかるを走らせることができました。嘘のようなホントの話、燃料消費が2024年より向上しました。しかしここまでの身体的ダメージによってか、椎間板ヘルニアの再発警報が腰と背中に響き渡っています。とりたくなくても齢をとってしまうなんて、理不尽だと思うんですが、日頃の鍛錬が足りないってことなんでしょう。
緊急入院の末病室で始まった2025年もどうにかこうにか大晦日まで這い蹲ってこられました。この1年で体重が30キロ削れました。例年並みのペースで5万キロ弱、BLUEらすかるを走らせることができました。嘘のようなホントの話、燃料消費が2024年より向上しました。しかしここまでの身体的ダメージによってか、椎間板ヘルニアの再発警報が腰と背中に響き渡っています。とりたくなくても齢をとってしまうなんて、理不尽だと思うんですが、日頃の鍛錬が足りないってことなんでしょう。
それはそれでまぁいいか。明日は明日です。ことしも沢山の人々にお世話になりました。来年は足手まといにならないよう精進します。とか言いながら、明後日はまた明日と異なるので、あてになりませんけど。
それでは良いお年を。
納まる気がしない今年の仕事納め
なつかれくさしょうず
 これを「乃東生」と綴るのが難しいというか、読めませんです。世間では冬至の方がポピュラーですが、どんどん冬が深まっていく中、ほとんどの草木が枯れていく中で、ウツボ草だけは芽吹いてくる時期で、そのことを記しているのが「なつかれくさしょうず」。そんな地上の営みとは関係なく、公転周期と地軸の角度の関係によって、当時の頃は昼の時間が10時間を下回る、朝が来るのも遅めの時期です。記事の方も「乃東生」と関係なくなっていきます。素直に冬至のことだけ書けよってなもんです。
これを「乃東生」と綴るのが難しいというか、読めませんです。世間では冬至の方がポピュラーですが、どんどん冬が深まっていく中、ほとんどの草木が枯れていく中で、ウツボ草だけは芽吹いてくる時期で、そのことを記しているのが「なつかれくさしょうず」。そんな地上の営みとは関係なく、公転周期と地軸の角度の関係によって、当時の頃は昼の時間が10時間を下回る、朝が来るのも遅めの時期です。記事の方も「乃東生」と関係なくなっていきます。素直に冬至のことだけ書けよってなもんです。
スーパーフレックスな仕事時間の関係により、湾岸線から晴海に向かって都内にたどり着く頃、まだ空は夜の景色です。豊洲のあたりで気がついたのは、ほんのわずかな時間、ほんとうに一瞬に近く、東京タワーの光が見えることです。日中、ここを通ってもわからなかった。
一方、東京スカイツリーは都心の外延部にあることから、中央環状線や豊洲より東の湾岸線からならばまだ遮るものが無い。無いけれど、なんかこう、見えているからといってありがたみも無い。これは世代なんでしょう、東京タワーが見えるとなんとなく嬉しい。寒々とした冬の大気をまとった時期ならではの眺めです。
・・・なにが冬至なんだかこの記事
高速周回路跡 今では跡形もないです
 BLUEらすかるを手に入れた頃の谷田部テストコース跡は、まだバンクがそのまま残されていて、このあたりに建つ商業施設群の影も形も無かったのですが、今はバンク跡の方が跡形もなくなってしまいました(別の場所に切り刻まれたバームクーヘンじゃあるまいし、のようなオブジェ化したものが残ってはいますが)。このまま放置しておくと、乗り込んじゃう輩も出てきて危険と言えば危険でしたから撤去されるのも仕方ないのですが。
BLUEらすかるを手に入れた頃の谷田部テストコース跡は、まだバンクがそのまま残されていて、このあたりに建つ商業施設群の影も形も無かったのですが、今はバンク跡の方が跡形もなくなってしまいました(別の場所に切り刻まれたバームクーヘンじゃあるまいし、のようなオブジェ化したものが残ってはいますが)。このまま放置しておくと、乗り込んじゃう輩も出てきて危険と言えば危険でしたから撤去されるのも仕方ないのですが。
 今やテストコースは県北部に移転し、筑波はつくばと呼ばれるようになって、かつては自動車産業の一ジャンルとして様々な試験実験が行われていた昭和史も夢のあとです。谷田部と聞くと、自動車雑誌での企画記事をよく思い出しますが、つくばエクスプレスの沿線開発はいとも簡単にモータリゼーション文化の一大拠点を消し去ってしまったのだなと感じます。デビュー当時のスズキエスクードも、この周回路を走らせた記事が残されています。
今やテストコースは県北部に移転し、筑波はつくばと呼ばれるようになって、かつては自動車産業の一ジャンルとして様々な試験実験が行われていた昭和史も夢のあとです。谷田部と聞くと、自動車雑誌での企画記事をよく思い出しますが、つくばエクスプレスの沿線開発はいとも簡単にモータリゼーション文化の一大拠点を消し去ってしまったのだなと感じます。デビュー当時のスズキエスクードも、この周回路を走らせた記事が残されています。
 メガトン怪獣に降ってこられたらBLUEらすかるなどぺしゃんこですからそれは願い下げですが、天高い秋空そのものが写りこんでくれるのは歓迎です。朱の背景に青いものが紛れ込むと、主観としてはきれいには思えないのに、その逆だと青が朱を映えさせるのは不思議です。ただ、ブログ用に縮小をかけたらあまり目立たなくなってしまいました。といってトリミングしたら何を伝えたいのかもわからなくなってしまうところが撮り手の下手さを露呈しています。
メガトン怪獣に降ってこられたらBLUEらすかるなどぺしゃんこですからそれは願い下げですが、天高い秋空そのものが写りこんでくれるのは歓迎です。朱の背景に青いものが紛れ込むと、主観としてはきれいには思えないのに、その逆だと青が朱を映えさせるのは不思議です。ただ、ブログ用に縮小をかけたらあまり目立たなくなってしまいました。といってトリミングしたら何を伝えたいのかもわからなくなってしまうところが撮り手の下手さを露呈しています。
 秋が足早にやってきて、さっさと行ってしまうような今年の割に、里の紅葉がなかなかピークになりません。戦場ヶ原あたりまで行ってくれば見ごろだとは思いますがまあめんどくさくて、いろは坂の渋滞も経験したくない。うつろう風景の中にクルマなんか置くんじゃないよと言われそうなので、人のいないところを探すわけです。それもなかなか大変なんで、クルマの中に風景を刻む分には文句ないだろうと試したらこんな感じでした。
秋が足早にやってきて、さっさと行ってしまうような今年の割に、里の紅葉がなかなかピークになりません。戦場ヶ原あたりまで行ってくれば見ごろだとは思いますがまあめんどくさくて、いろは坂の渋滞も経験したくない。うつろう風景の中にクルマなんか置くんじゃないよと言われそうなので、人のいないところを探すわけです。それもなかなか大変なんで、クルマの中に風景を刻む分には文句ないだろうと試したらこんな感じでした。