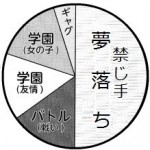劇場公開からは何カ月も遅ればせながらTHE NEXTGENERATIONパトレイバーの第五章を買ってきまして(遅れてるってもソフトの発売日は今日です)、エピソード8と9を観ました。狙撃手の話であるエピソード8は、何もわざわざパトレイバーでやることないじゃんというプロットながら、パトレイバーだとこういうのもありなのねと変に納得させられるのです。
劇場公開からは何カ月も遅ればせながらTHE NEXTGENERATIONパトレイバーの第五章を買ってきまして(遅れてるってもソフトの発売日は今日です)、エピソード8と9を観ました。狙撃手の話であるエピソード8は、何もわざわざパトレイバーでやることないじゃんというプロットながら、パトレイバーだとこういうのもありなのねと変に納得させられるのです。
ただし2000メートルという狙撃距離を主題とするシリアスにあたって、どこのビルにいるのかが視聴者にわかってしまうカメラアングルは良くない。2000メートルどころか30000メートルの距離で撃ちあってませんでしょうか?
それとは真逆のエピソード9は、こればかりはパトレイバーでなければだめだわという、埋め立て地の地下迷宮もの。かつてテレビシリーズとその後のOVAで2度、続き物として扱ったアレだというので、面白くないはずがない。
でもって、面白くないはずがないくらい前作のトレースだらけで、「それを特撮で大道具小道具再現した」という以外、何一つ生みの苦しみが無いぞという、オチにちょっとだけアレンジを加えたしょーもない出来栄えです。あー、極端に言えば出さなくてもいいイングラムを動かしたという部分は良かったのか。
だけど困ったことにパトレイバーの地下迷宮は面白くて笑ってしまう。