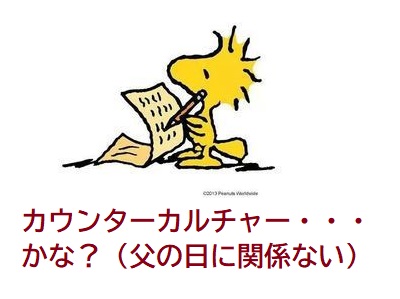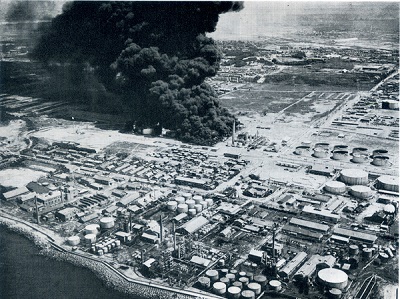日本ファーザーズ・デイ委員会、などというものが40年も活動していることなど知りませんでしたが、「父の日」という刷り込みはもっと以前に行われているのが僕の記憶です。だいたいが80年代と言ったら僕なんか、親父とは確執の年頃の時代ですよ(笑)
日本ファーザーズ・デイ委員会、などというものが40年も活動していることなど知りませんでしたが、「父の日」という刷り込みはもっと以前に行われているのが僕の記憶です。だいたいが80年代と言ったら僕なんか、親父とは確執の年頃の時代ですよ(笑)
それはともかく、父の日にイエローカラーを取り入れたのがこの委員会のようで、一時期はギフトコーナーが黄色の薔薇で溢れていた覚えがあります。
しかし当時、なんでまた「ジェラシー」とか「薄らぐ愛」とか「不貞」とか「別れ」とか、それって嫌がらせ用アイテム? と思わせる花言葉の黄色の薔薇を使うんだろう? と思っていました。銀河英雄伝説においては、かの疾風ウォルフなんか、それ買ってプロポーズに行っちゃったくらいだから、悪いだけのことではないかもしれません(まあミッターマイヤー氏の場合は世間知らずの引き合いに用いられた感が強いですが)
すると彩りと薔薇の話は別々のものが日本で混同したと。発祥のアメリカでは父親が健在か亡くなっているかで赤か白という、母の日のカーネーションと同様の送り方をするのが故事(最初に贈ったご婦人の父親が亡くなっていたので白から始まった)。この区別は、あとになって日本なんかでは差別的とも言われ出したので、父の日ではそこを避け、前述の委員会では黄色いリボンにイメージを託したのでしょう。
黄色いリボンは「無事に帰っておくれ」という祈願の意味があるそうで、そこから「幸福」だの「喜び」だの「希望」だのという象徴が定着しているイエローカラーが父の日にふさわしいとなっていたようですが、遅かったよ、僕なんか黄色はゲルショッカーカラーやらショッカーライダー1号やらが焼き付いてましたから。
もう労いの贈り物をすることも叶わなくなった僕の親父はちょっとかわいそうで、何の因果か6月20日が誕生日でした。つまりかなりの確率で、誕生祝と父の日贈答がひとまとめにされていました。といったって、確執していながらこれを毎年欠かさなかったのは大したものです我ながら。
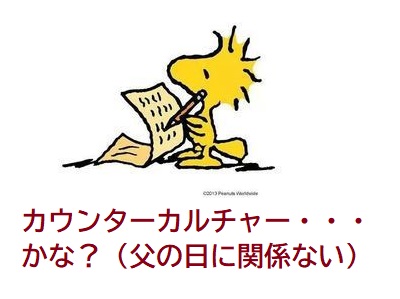 さて困ったよ。父の日について書き出したらあらぬ方向へ迷走していますよ。いくつかのまとめサイトを読んでみましたが、どこもかしこも受け売り内容ばかりで、薔薇と黄色の接点は遂にわからなかった。黄色で思い出して「ウッドストック」を引いたらほんとにトップクラスでこの鳥が出てくるのもびっくりでしたが、キツツキだと言いきっているところがあるのも驚きです。むしろ彼の名は世相を背負っているはずなんだけれど・・・
さて困ったよ。父の日について書き出したらあらぬ方向へ迷走していますよ。いくつかのまとめサイトを読んでみましたが、どこもかしこも受け売り内容ばかりで、薔薇と黄色の接点は遂にわからなかった。黄色で思い出して「ウッドストック」を引いたらほんとにトップクラスでこの鳥が出てくるのもびっくりでしたが、キツツキだと言いきっているところがあるのも驚きです。むしろ彼の名は世相を背負っているはずなんだけれど・・・
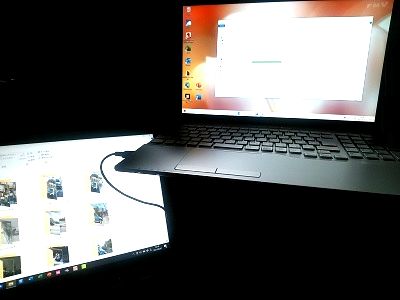 いま、手元で作業に使われているノートパソコンは通算11代目にあたりますが、今年に入って内臓ファンから異音が出始め、その部分のエラーが起動時に警告を出すようになってしまいました。
いま、手元で作業に使われているノートパソコンは通算11代目にあたりますが、今年に入って内臓ファンから異音が出始め、その部分のエラーが起動時に警告を出すようになってしまいました。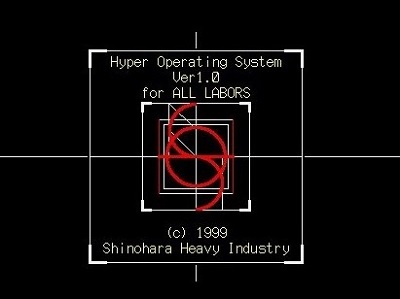 一方、新たに起動した13号機は、同じシリーズで同じOSなのに、いろいろと仕様変更されていてかなり使いにくい。さて古すぎる動画は動かない。さて困ったぜと。この際、もう少し11号機に頑張ってもらって、徐々に新しいやつの操作を覚えるとするか。と思ったわけですが、パッケージを開けたらメディアが入っていないソフトの売り方ってやめてよーっ(プロダクトキーとシリアルナンバーでログインしてダウンロードの時代だということを知らない)
一方、新たに起動した13号機は、同じシリーズで同じOSなのに、いろいろと仕様変更されていてかなり使いにくい。さて古すぎる動画は動かない。さて困ったぜと。この際、もう少し11号機に頑張ってもらって、徐々に新しいやつの操作を覚えるとするか。と思ったわけですが、パッケージを開けたらメディアが入っていないソフトの売り方ってやめてよーっ(プロダクトキーとシリアルナンバーでログインしてダウンロードの時代だということを知らない)