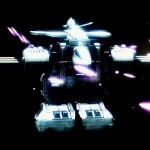暇を見つけては見てきた「無敵鋼人ダイターン3」。前作の「無敵超人ザンボット3」が、報われはしても救われない物語だっただけに、がらりと趣向を変えてエンターテインメントさを押し出しながらも、やっぱり影と過去を背負った男の救われないバックボーンがちらついていく。
暇を見つけては見てきた「無敵鋼人ダイターン3」。前作の「無敵超人ザンボット3」が、報われはしても救われない物語だっただけに、がらりと趣向を変えてエンターテインメントさを押し出しながらも、やっぱり影と過去を背負った男の救われないバックボーンがちらついていく。
40話もありながら、柱だけを拾っていくと極めてシンプルなストーリーが浮き彫りにされてきます。
てことは、これって2時間くらいの映画としてそこだけ抽出できるんじゃないか?
そう思いながらも、この時代のアニメーションとして斬新だったはずのダイターン3も、しみじみと見直すと、とんでもなく作画のレベルが低く、よくこんなのを毎週見ていて飽きなかったもんだわと思わされます。
しかし作画がダメだという話ではなくて、そこを妥協しないと毎週一話の放送にはとても間に合わなかったのであろうという、劣悪な労務環境がにじみ出ているのです。これをやりながら次回作を企画していたことを想像すると、まさしく「僕は いやだ!」という叫びが聞こえてきそうです。
 次回作となる「機動戦士ガンダム」が、まだプロット段階であった頃は、まったく別物のロボットアニメで、どうやらそのエッセンスは後に「伝説巨神イデオン」と「銀河漂流バイファム」に分かれていったようです。
次回作となる「機動戦士ガンダム」が、まだプロット段階であった頃は、まったく別物のロボットアニメで、どうやらそのエッセンスは後に「伝説巨神イデオン」と「銀河漂流バイファム」に分かれていったようです。
ガンボイという仮題がガンダムに改められ、骨子がまとまっていく中でも、主役ロボットの色稿がスポンサーと玩具販売を意識して、こんなデザインと色彩だったわけです。
そりゃーいやになっちゃうだろうなあ。
「機動戦士ガンダム」の作画とリミテッドアニメの関係で目を引くのは、敵側のモビルスーツの色彩が、極力色数を抑えていたこと。アニメーターの作業量を減らすことができて、使い回しのバンクショットにも多用できるという効能があります。実は「無敵鋼人ダイターン3」でも同じことが行われているのですが、こちらは前者に対する苦肉の策だったのでしょう。絵の具の選択自体がめちゃくちゃ。二度は使えないよこんなの(いっぺん使ってましたが)というひどいものでした。
「僕は いやだ!」は、主人公破嵐万丈の最後の台詞。もちろんこれは、物語の中で吐き出された、全く異なる意味を持った一言です。アニメの作り方とは何も関係がありません。深読みをする必要もない。にもかかわらず、今これを見ていると、また別の言葉として聞こえてくるのが不思議なものです。
なんだかんだ言って、現在の作画のとんでもなくレベルアップしたそれよりも、味があるというところ。ひょっとすると、それかなあと思っています。つまりは、今の作画なんかで、万丈は活躍したくないんじゃないかと。復活だとか映画化だとかは、やっぱり無理な相談か・・・
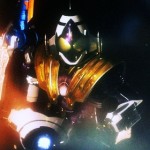 あまりにも雑誌やインターネット上の前フリ情報が多すぎて、観に行く前から起承転結全部わかってしまうのは、その情報に直接さらされている子供達であって、想像力も緊迫感も与えない宣伝というのは問題だなあと感じました。
あまりにも雑誌やインターネット上の前フリ情報が多すぎて、観に行く前から起承転結全部わかってしまうのは、その情報に直接さらされている子供達であって、想像力も緊迫感も与えない宣伝というのは問題だなあと感じました。