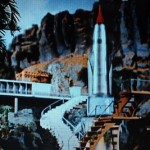何をどう企画されようとも手を出さなかったディアなんとかの配本に、とうとうつかまってしまいました。「サンダーバード」は、実はDVDボックスを持っているのですが、今回のディアなんとかのやろー、「ジェリー・アンダーソンの世界」と銘打ち、「キャプテンスカーレット」「海底大戦争スティングレイ」「謎の円盤UFO」「ジョー90」をまとめてきやがりました。むむむ・・・「UFO」は・・・これは欲しい。って、はっきり言って「UFO」だけが欲しいなら、そのDVDボックスを中古で探して買ってきた方が、安上がりじゃねーかと。
何をどう企画されようとも手を出さなかったディアなんとかの配本に、とうとうつかまってしまいました。「サンダーバード」は、実はDVDボックスを持っているのですが、今回のディアなんとかのやろー、「ジェリー・アンダーソンの世界」と銘打ち、「キャプテンスカーレット」「海底大戦争スティングレイ」「謎の円盤UFO」「ジョー90」をまとめてきやがりました。むむむ・・・「UFO」は・・・これは欲しい。って、はっきり言って「UFO」だけが欲しいなら、そのDVDボックスを中古で探して買ってきた方が、安上がりじゃねーかと。
わかっているのだけれど、5作品トータルで考えて妥協してしまいました(全54回だってよー。かなりかさばるんじゃないか?)
というわけで少し前のことですが、第1巻を買ってみたわけですが、どんな世代の人がこのデータブックとなるファイルの編集をやっているんだろうなあ。まずNHKでの本放送を当時オンタイムで見ていた世代じゃなかろうなと思いながら、TB2号の内部図解にある原子炉のことを「安全型融合炉」なんて打ち換えちゃうのが時代の哀しさかと感じます。
その描写に関しては極めて楽観的な描き方が目立ったものの、サンダーバードは、幾度か原子力災害にも出動していて、科学万能論に対するアンチテーゼもうたっていました。国際救助隊もまた、TBメカニックの動力には原子力を使っており、使っているからこそ運用のリスクを背負っているところに、パラドックスとリアリティが感じられました。今回、最新の図解を見て思ったのだけれど、60年代にも「安全型融合炉」なんて言っていたのかなあ?
でもってその話は長くなるので割愛。いいトシこいて何度も見ていて、今さらこれに気がつかなかったのかとこっ恥ずかしい思いなのですが、TB1号の発進シークエンスは、2号、3号とともに、日本の特撮番組に多大な影響を及ぼした名シーン。孤島のトレーシー邸前面にあるプール(子供のころ読んだ雑誌には、ひょうたん型プールと書かれていた)がスライドして、発射サイロを開くのはいちいち説明する必要もありません。
発射までの流れを挿絵でポイントだけ押さえてみました。1号はトレーシー邸リビング、つまり指令所の壁の向こう側に格納されており、長男スコット・トレーシーは直立している機体に乗り込み、その搭乗ハッチのある側から、サイロに向かって斜行エレベータで降下と同時に水平移動していきます。このとき機体はリビング・指令所の真下をくぐってサイロへ向かっていくのですが、斜行エレベータにはターンテーブルもそなわっているらしく、サイロのフロアに降りてくる途中で、機体の向きが90度回転しているのです。
なんで? ってそれはまあ、テレビ映りの見栄えの話なのですが、こういうところに科学的な解釈など必要なかったのが、60年代だったのですね。これが、アムロ・レイがホワイトベースのブリッジからモビルスーツデッキまでどうやって移動するのかという話になってくると、そんなのどうでもいいじゃんとはいかなくなる。
でも、TB1号はなぜ機体を回転させる必要があるのか。この回転時に外観からの最終点検をやっているのか? 単にサイロ開口部のプールの形状に、機体の前面投影面積を合わせる必要があっただけなのか。
実は設定を知らないだけなのかもしれませんが、僕の中では謎なのです。
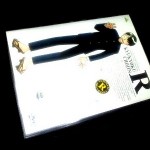 基地にはVHSのレンタル版とセル版があります。実は双方、特典映像の置き方が異なっているのです。しかしDVDはいつ売り出されていたかを知らないため、今頃になって中古ソフトが手元にやってくるというありさまです。
基地にはVHSのレンタル版とセル版があります。実は双方、特典映像の置き方が異なっているのです。しかしDVDはいつ売り出されていたかを知らないため、今頃になって中古ソフトが手元にやってくるというありさまです。