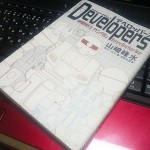今さら気づくのが遅いよと言われてしまう、仮面ライダー1号、2号のニューサイクロンに生じている、同型でありながら実際には仕様の差異に、今後のスピンオフを期待してしまう自分なのであります。
今さら気づくのが遅いよと言われてしまう、仮面ライダー1号、2号のニューサイクロンに生じている、同型でありながら実際には仕様の差異に、今後のスピンオフを期待してしまう自分なのであります。
今年公開されている「レッツゴー仮面ライダー」では2号ライダーが使っている車体は、往年のライダーマシンに対して、車両協力を続けてきたスズキのバイクがベースとして復活しています。写真は2年前にオールライダー勢揃いとなった「仮面ライダーディケイド」映画のシーンで、ここでは1号が乗っています。
写真に基づき、1号のニューサイクロンを紐解くと、これがたぶん、スズキRM250あたり(125じゃないよね?)をベースにしており、エンジンは水冷2サイクル単気筒。年度モデルは異なりますが、仮面ライダースーパー1が乗ったブルーバージョンで、ベースマシンとして使われたことがあります。モトクロス競技用車両としての実績を重ねてきたバイクで、スーパー1の撮影時には瞬発力とサスペンションの性能が上がり(それ以前のベースマシンに対して)、スタントシーンでも驚異的なジャンプを見せたという逸話があるそうです。このブルーバージョンも、番組後半では4サイクルエンジンのSP370にスイッチされています。
1993年のオリジナルビデオ?「ウルトラマンVS仮面ライダー」にもRMベースのニューサイクロンが登場していたとのことですが、その車体と2009年以降の車体が同一かどうかは、年次差から考えて、疑ってかかかった方がいいでしょう。その後オートレースのCMにも、パチンコのCMにも登場しているようですから、それらの車体が近いのかもしれませんし、今回何度目かのRM採用なのかもしれません。しかしベースマシンでホンダ勢力圧倒的な昨今、XRの1台くらいけちけちするとも思えないわけで、2009年に2台のXRベースが用意されなかったということは、RMベースの車体が残っていたと考えていきたいところです。
排ガス規制や環境課題への対策から、2ストエンジンは生産が終了していき、4ストエンジンへと移り変わってきたのが自動2輪の世界。今やそれでもパワー・トルクの出方には遜色のない性能が安定しているし、なにより市販車そのものが、旧サイクロンを凌駕する最高速度を引き出してしまう世の中です。わざわざ原子力エンジンを搭載などと、見え透いた嘘をつかなくとも、仮面ライダーのマシンは成立してしまう。それでも、うねったチャンバーと、独特の鼓動は、別の意味で郷愁を誘うところがあります。
仮面ライダーの世界で、2ストだ4ストだという市販エンジンのことを語るのは、世界観の設定上、無理があるのは承知なのですが、ニューサイクロンだけに限って言うと、一部の客演マシンを除いて、ベースマシンはTS250の3型(実はライダーマンマシーンは4型に進化している)でしたから、これが代替わりしている。考えてみれば40年もショッカーたちと戦っていて、ニューサイクロンからこっち、愛車をフルモデルチェンジさせていないのが、彼らの不思議なアイデンティティーです。しかしTSからRMへ、メーカーをまたいでXRへと、中味を変えている。その2台のうち1台が、依然として2ストのエンジンを搭載しているところに、本郷猛と一文字隼人、あるいは立花藤兵衛の思い入れを探してみたくなるのです。