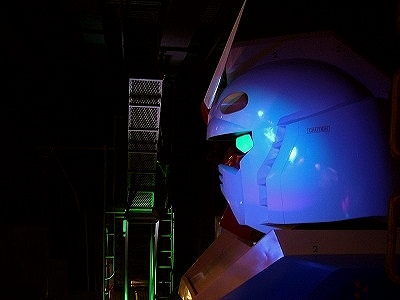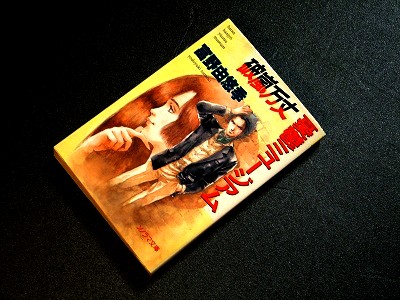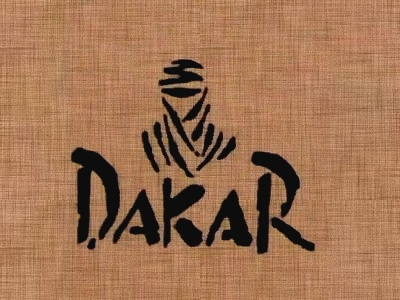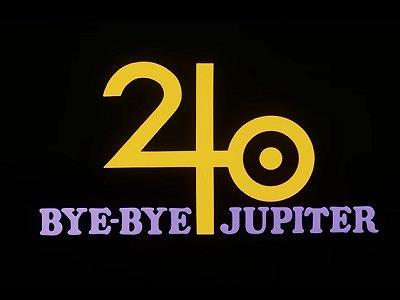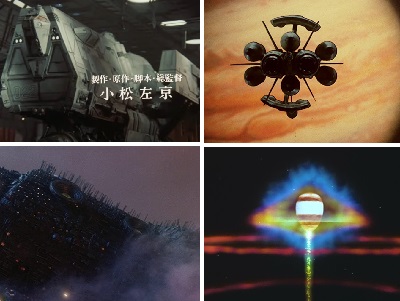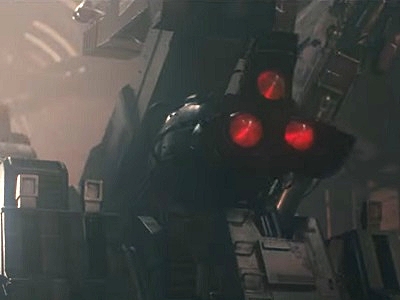1994年4月16日、「仮面ライダーJ」の劇場映画が封切られました。登場年次で言えば平成版仮面ライダーなのですが、前作「仮面ライダーZO」、次作「真・仮面ライダー序章」の3作は「ネオライダー」とまとめられているのが不思議です。しかし「J」には71年から累々と続いてきたライダーを巨大化させるという、初期に一度浮かんで消えたアイデアを具現化したという革新が込められていました。GiantでなくJumboというネームにもセンスがあります。
1994年4月16日、「仮面ライダーJ」の劇場映画が封切られました。登場年次で言えば平成版仮面ライダーなのですが、前作「仮面ライダーZO」、次作「真・仮面ライダー序章」の3作は「ネオライダー」とまとめられているのが不思議です。しかし「J」には71年から累々と続いてきたライダーを巨大化させるという、初期に一度浮かんで消えたアイデアを具現化したという革新が込められていました。GiantでなくJumboというネームにもセンスがあります。
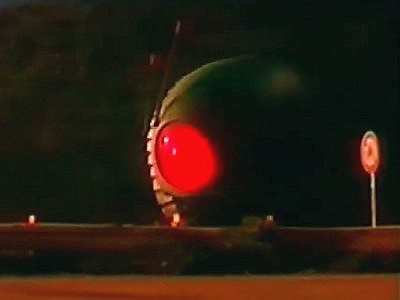 ライダーの巨大化は前年に「ウルトラマンvs仮面ライダー」で新1号がやってのけています。それでも「J」を推すのは「ウルトラ~」の方はもう漫画でしか無いよという巨大化必然だったからです。長年等身大でやってきた仮面ライダーをどのように巨大ヒーローとして見せるか。という工夫が「J」のジャンボフォーメーションでは丹念に描かれていました。残念なのは、後発ライダー映画への客演時、巨大化ぶりが雑に描かれていたことです。
ライダーの巨大化は前年に「ウルトラマンvs仮面ライダー」で新1号がやってのけています。それでも「J」を推すのは「ウルトラ~」の方はもう漫画でしか無いよという巨大化必然だったからです。長年等身大でやってきた仮面ライダーをどのように巨大ヒーローとして見せるか。という工夫が「J」のジャンボフォーメーションでは丹念に描かれていました。残念なのは、後発ライダー映画への客演時、巨大化ぶりが雑に描かれていたことです。
 ところで更に遡ること1974年4月17日、「ウルトラマンレオ」が始まるのですが、「レオ」もウルトラのシリーズでは初の「M78星雲出身ではない」ウルトラマンとして企画されました。無念にも第二次怪獣ブームは下火を迎え、視聴率低迷と打ち切りやら延長やらコスト縮減やらの憂き目に遭い身内が全滅するに至るものの、無理やりスポ根もの要素を持ち込んで戦士を鍛え上げる初期の設定自体がどうかしていたようにも感じられます。
ところで更に遡ること1974年4月17日、「ウルトラマンレオ」が始まるのですが、「レオ」もウルトラのシリーズでは初の「M78星雲出身ではない」ウルトラマンとして企画されました。無念にも第二次怪獣ブームは下火を迎え、視聴率低迷と打ち切りやら延長やらコスト縮減やらの憂き目に遭い身内が全滅するに至るものの、無理やりスポ根もの要素を持ち込んで戦士を鍛え上げる初期の設定自体がどうかしていたようにも感じられます。
 隊長がウルトラ戦士という設定は、ヒルマ・ゲントさんよりも早くモロボシ・ダンがウルトラセブンでありMACの指揮官として描かれましたが、ダンの立ち位置のせいなのかレオの戦士としての履歴の浅さなのか、ウルトラ警備隊において異星人の視点から地球防衛に疑問を感ずる事さえあったダンも、性格が変われば変わるものだと思うくらい、しごきの鬼に変貌していました。毎回見ている方が辛くなる番組でしたが、レオの造形も含めて革新的なウルトラであったことは確かです。
隊長がウルトラ戦士という設定は、ヒルマ・ゲントさんよりも早くモロボシ・ダンがウルトラセブンでありMACの指揮官として描かれましたが、ダンの立ち位置のせいなのかレオの戦士としての履歴の浅さなのか、ウルトラ警備隊において異星人の視点から地球防衛に疑問を感ずる事さえあったダンも、性格が変われば変わるものだと思うくらい、しごきの鬼に変貌していました。毎回見ている方が辛くなる番組でしたが、レオの造形も含めて革新的なウルトラであったことは確かです。