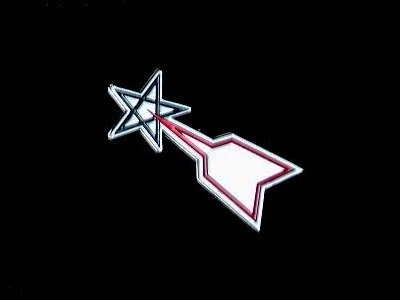 円谷英二さんが映画の世界と邂逅するのは18歳のとき。1919年のことです。経緯は端折りますが、いま、生誕の地須賀川市で建設されている市民交流センター「tette」に、円谷さんの生涯を紹介するミュージアムが内包される予定で、施設全体が2019年1月に開館する。奇しくも円谷映像職人の誕生から100年めで、英二さんの世界が須賀川に帰還することとなります。ウルトラマンをはじめゴジラ(1954年版を中心に)の展示が考えられているそうです。
円谷英二さんが映画の世界と邂逅するのは18歳のとき。1919年のことです。経緯は端折りますが、いま、生誕の地須賀川市で建設されている市民交流センター「tette」に、円谷さんの生涯を紹介するミュージアムが内包される予定で、施設全体が2019年1月に開館する。奇しくも円谷映像職人の誕生から100年めで、英二さんの世界が須賀川に帰還することとなります。ウルトラマンをはじめゴジラ(1954年版を中心に)の展示が考えられているそうです。
 まだ市内の松明通りにウルトラ兄弟や怪獣のモニュメントなど無く、電線地中化で設置された点検ボックスにウルトラ影絵が描かれた時代、僕が須賀川を訪れたのは平成の始まった頃でした。当時は青年会議所が円谷英二記念館構想を論じていて、科学特捜隊の流星マークをモチーフとした建物のイメージが描かれていましたが、これが実現することはなく、しかし松明通りや福島空港などを拠点にして、ウルトラマンの世界観をアピールする仕掛けは地道に続けられてきました。
まだ市内の松明通りにウルトラ兄弟や怪獣のモニュメントなど無く、電線地中化で設置された点検ボックスにウルトラ影絵が描かれた時代、僕が須賀川を訪れたのは平成の始まった頃でした。当時は青年会議所が円谷英二記念館構想を論じていて、科学特捜隊の流星マークをモチーフとした建物のイメージが描かれていましたが、これが実現することはなく、しかし松明通りや福島空港などを拠点にして、ウルトラマンの世界観をアピールする仕掛けは地道に続けられてきました。
 東日本大震災での内陸地震被害を大きく受けた須賀川市が、復興事業の一環として市内の中心地で閉鎖されてしまった施設の解体と新築を実行し、市民交流センターが実現したそうです。「建物の中にウルトラマンの部屋ができるんですよ」と、関係者の声を聞いたのが建物の着工の頃で、地元にしてみれば30年来の努力が実るのだなあと感じさせられたものです。今日7月7日は、英二さん生誕117年めの日。松竹映画入社後第1作の『怪盗沙弥磨』から90年を迎えます。
東日本大震災での内陸地震被害を大きく受けた須賀川市が、復興事業の一環として市内の中心地で閉鎖されてしまった施設の解体と新築を実行し、市民交流センターが実現したそうです。「建物の中にウルトラマンの部屋ができるんですよ」と、関係者の声を聞いたのが建物の着工の頃で、地元にしてみれば30年来の努力が実るのだなあと感じさせられたものです。今日7月7日は、英二さん生誕117年めの日。松竹映画入社後第1作の『怪盗沙弥磨』から90年を迎えます。







 新型は前評判の頃から受けが良いようでしたが、K型からR型にエンジンを載せ替えたことと、トランスファレバーを復活させたこと、衝突安全回避装備の他には、今さら変えようがないんですというくらいDNAとやらを踏襲しています。ご意見番の言葉は「古い技術ではない。培われた良い技術は活かそう。原点に還すのだ」であったそうです。なにしろモノコックジムニーの案もあったらしいので、その白紙撤回は大命題だったのでしょう。まあ骨格やメカニズムはその方が良いこともあります。しかし・・・
新型は前評判の頃から受けが良いようでしたが、K型からR型にエンジンを載せ替えたことと、トランスファレバーを復活させたこと、衝突安全回避装備の他には、今さら変えようがないんですというくらいDNAとやらを踏襲しています。ご意見番の言葉は「古い技術ではない。培われた良い技術は活かそう。原点に還すのだ」であったそうです。なにしろモノコックジムニーの案もあったらしいので、その白紙撤回は大命題だったのでしょう。まあ骨格やメカニズムはその方が良いこともあります。しかし・・・ それほどJBシリーズは不評だったのかと、つい二代目エスクードとオーバーラップさせるのですが、新型のデザインは温故知新というよりやけくそだと感じてなりません。JBがいかに冒険したトライアルだったか。クロカン四駆=軍用車を「すり込まれた世代のステレオタイプなロジック」から抜け出そうとしたことだと思うからです。いま、ミリタリーが好まれるなら仕方ないけれど、それに憧れた昔の人々の押しつけじゃないか。コンサルティングの言いなりのようなデザインが、戦後すら関わりの薄れた世代に向けた、メーカーからのメッセージなんて情けない。
それほどJBシリーズは不評だったのかと、つい二代目エスクードとオーバーラップさせるのですが、新型のデザインは温故知新というよりやけくそだと感じてなりません。JBがいかに冒険したトライアルだったか。クロカン四駆=軍用車を「すり込まれた世代のステレオタイプなロジック」から抜け出そうとしたことだと思うからです。いま、ミリタリーが好まれるなら仕方ないけれど、それに憧れた昔の人々の押しつけじゃないか。コンサルティングの言いなりのようなデザインが、戦後すら関わりの薄れた世代に向けた、メーカーからのメッセージなんて情けない。 しかし今回、1500を搭載するシエラは間違いなく注目株。あくまでもジムニーは軽自動車規格であるとしても、です。一般視線から見れば、テンロクエスクード・ショートの再来と言ってもいいからです。これに4ドア・・・じゃなくてもいいから
しかし今回、1500を搭載するシエラは間違いなく注目株。あくまでもジムニーは軽自動車規格であるとしても、です。一般視線から見れば、テンロクエスクード・ショートの再来と言ってもいいからです。これに4ドア・・・じゃなくてもいいから
 マミポコさんが送ってきてくれた写真を見て、ぎょっとしたのに、ブログに揚げてみたらなんでもなくなってしまった。
マミポコさんが送ってきてくれた写真を見て、ぎょっとしたのに、ブログに揚げてみたらなんでもなくなってしまった。 その状況を、PrtScで切り取り再生してみましたが、やはり普通で説明のしようがない。どんなだったのかを再現するため、こちらで強制的にRGBをいじったのが下のファイルです。
その状況を、PrtScで切り取り再生してみましたが、やはり普通で説明のしようがない。どんなだったのかを再現するため、こちらで強制的にRGBをいじったのが下のファイルです。



